タンパク質は一度に30gまでしか吸収されない。筋トレをしている人なら、一度は聞いたことがあるこの常識。でも、それ…本当に正しいと思いますか?
僕自身、この言葉を信じて、せっせと1日4回に分けてタンパク質を摂取していました。しかし、科学的な知見と自分自身の身体の変化を追いかけていく中で、はっきりと気づきました。この常識は、根拠の誤読と誤解から生まれた神話に過ぎないと。
本記事では、「1食に摂れるタンパク質量に上限はあるのか?」というテーマに対し、 科学的研究と筋トレ実践者としてのリアルな体験、この2つの視点から徹底解説していきます。無駄な努力はしたくない、本当に身体を変えたい、そう思う方にこそ、ぜひ読んでほしい内容です。
そもそもタンパク質とは?
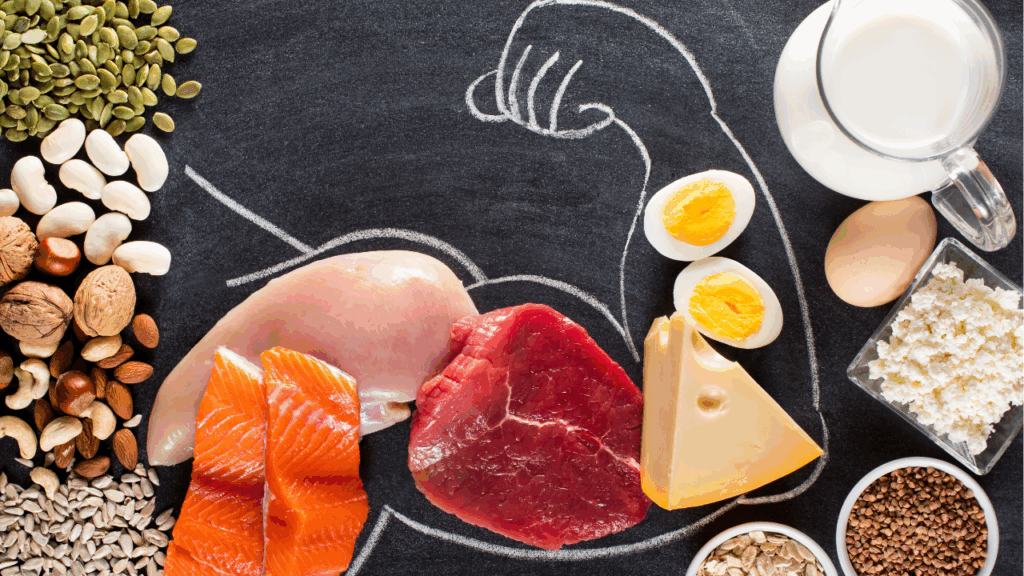
• 2-1. タンパク質は「筋肉だけじゃない」
筋トレといえば「プロテイン=タンパク質=筋肉」というイメージが強いですが、タンパク質の役割はそれだけにとどまりません。
• 筋肉・臓器・皮膚・髪・爪などの材料
• ホルモンや酵素、抗体の材料
• 神経伝達物質の生成にも関与
私たちの身体の構造や調整機能のほぼすべてに、タンパク質は関わっています。
• 2-2. 身体の修復・ホルモン・免疫など幅広い役割
運動によって壊れた筋繊維の修復はもちろん、
ストレスに耐えるホルモン(コルチゾール)や、免疫力の維持にも不可欠です。つまり、タンパク質は「筋トレをしている人だけの栄養素」ではないということ。むしろ、全人類が意識すべき栄養素なんです。

タンパク質は「筋肉の材料」ではなく、人間のベースを支える生命構成物質。
一度に吸収できるタンパク質量は○gは本当か?
• 3-1. よく聞く「20g〜30g説」の正体
一度に摂れるタンパク質は20gまで、30g以上は無駄。あとは脂肪になるだけ。こうした情報を見たことがある方も多いと思います。
SNSやフィットネス系のYouTube、本などでも、よく語られている常識のひとつです。実はこの説、まったく根拠がないわけではありません。
ただし、正確には「誤解されたまま独り歩きしてしまった情報」なんです。
▶︎この説の元ネタは「筋タンパク質合成(MPS)」に関する研究
タンパク質を摂ると、体内で「筋タンパク質合成(MPS)」というプロセスが活性化します。これは、簡単に言えば「筋肉を作るスイッチが入る」ようなもの。ある研究では、若い成人に20g〜25gのホエイプロテインを摂取させたところ、MPSが最大化されたという結果が出ました。つまり、筋肉の合成という目的に限って言えば、20〜25gで“最大効果”は発揮されるというわけです。
▶︎でも、それ=「それ以上は無駄」ではない
ここが最大の誤解ポイントです。
その研究が示したのはあくまで最大刺激が得られるラインであって、
「それ以上摂っても意味がない」とは書いていません。
実際には、体が余ったタンパク質を無視したり、すぐに排出したりすることはなく、消化されたアミノ酸は筋肉以外の修復、ホルモンの材料、酵素の合成など、全身で有効活用される仕組みになっています。
また、筋トレ歴や体重、筋量が多い人であれば、“最大刺激量”自体がもっと高い可能性があるのです。
▶︎たとえるなら「電池を満タンにする話」
この「20gが限界説」は、よく“充電”に例えられます。たとえば、スマホのバッテリーが100%になったら、それ以上充電しても増えませんよね。
でも、タンパク質摂取はそれとは違って、スマホに充電するだけじゃなく、別の端末にもシェアできるようなもの。つまり、筋肉が100%充電された後も、余った分は肝臓や皮膚や酵素など、他の「端末」にどんどん使われていくイメージです。
▶︎結論:「30g以上は無駄」は科学的に正しくない
筋合成の観点で最大刺激が得られる量は存在します。
でもそれは無駄のラインではなく、あくまで「ひとつの目安」にすぎません。トレーニング経験が長い人、体格が大きい人、高強度の運動をした人は、1回に30g以上摂ったほうがむしろ効率がいいケースも多々あります。
また、1日3食では必要量を満たせない場合、1食あたり40〜50g摂取する方がむしろ現実的で合理的です。
• 3-2. 実は吸収と利用は別物
ここで重要なのは、「吸収」と「筋合成への利用」は別であるということ。
胃腸は摂取したタンパク質をしっかり吸収・分解してアミノ酸にし、
それが身体のあらゆる部位に“時間差”で使われていきます。つまり、「30g以上は全部トイレに流れる」なんてことはありません。余剰分は、筋肉以外の内臓・皮膚・酵素合成などに回るほか、次の食事までの栄養バッファーとしても活用されます。
• 3-3. 科学的に見た「タンパク質摂取の柔軟性」
実際には、体格・筋量・年齢・トレーニング状況によって、必要量は変化します。たとえば体重70kgのトレーニーであれば、1日に体重×2g=140gのタンパク質が必要とされます。これを1日4食で割ると、1食あたり35g。
現実的に見ても、30gオーバーを1食で摂ることは、普通にありますし、むしろ効率的です。
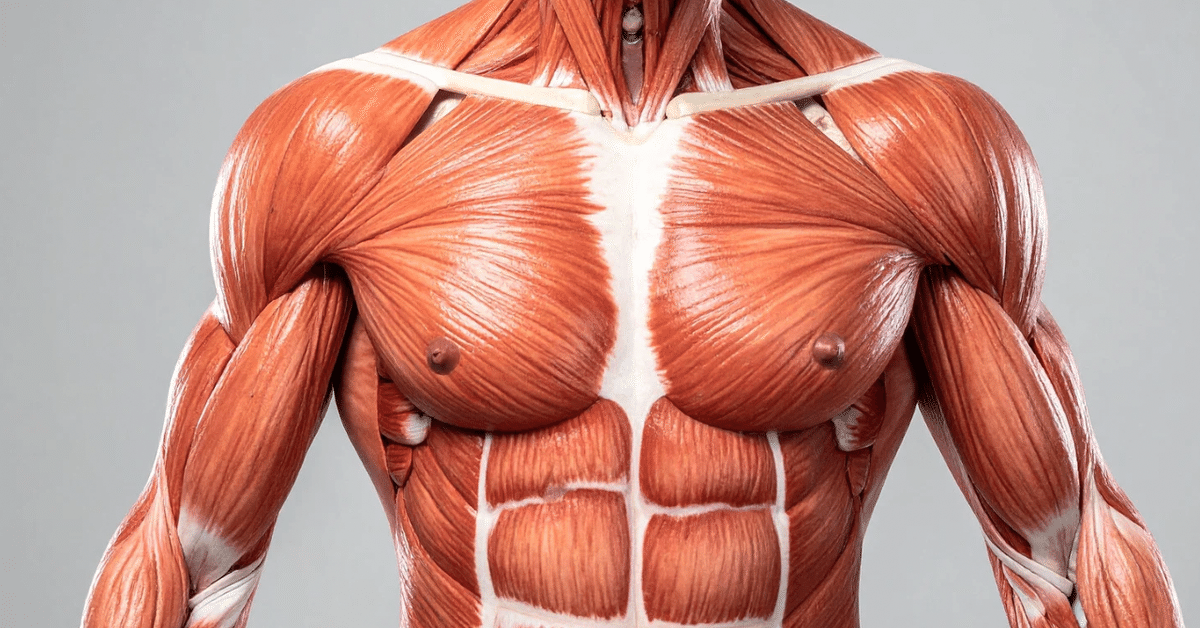
一度に吸収できる量は決まっているではなく、どう使われるかが大事。
実際に筋トレ実践者がやっていること
• 4-1. 一食で40g以上摂ることも普通
僕自身も、筋トレ後の食事では
• 鶏むね肉 150g(30g)
• ゆで卵 2個(12g)
• プロテイン1杯(20g)
といったように、50g近く摂ることもザラです。実際、そうした食事を続けてきた結果、筋肉量も代謝も向上しています。
• 4-2. それでも筋肥大・回復が進む理由
「超過分は無意味になる」というのは、栄養学の現場では否定されつつあります。実際には、“筋合成以外”の多様な役割にアミノ酸が使われているため、体全体の健康やパフォーマンスに貢献してくれるのです。
タンパク質だけじゃダメ?身体づくりの落とし穴
• 5-1. 摂取タイミングも重要
たとえ必要量のタンパク質を摂っていたとしても、摂取タイミングがズレていると効果が薄まることがあります。
• トレーニング後30〜60分以内に摂取(いわゆる「ゴールデンタイム」)
• 就寝前は吸収がゆっくりなカゼイン系がベター
• 朝にしっかり摂ると1日全体の代謝が活性化する
• 5-2. 炭水化物と脂質の役割
タンパク質だけを増やせば体が変わる、というのは危険な誤解です。
• 炭水化物(糖質)はトレーニングのエネルギー源であり、筋肉合成のスイッチを入れるインスリン分泌も促進
• 脂質はテストステロンなどのホルモン合成に不可欠。摂りすぎはNGですが、過度に避けると逆効果つまり、筋肉を育てるには、バランスが重要。
どれかを極端にカットしたり、タンパク質ばかりに偏ったりするのは、パフォーマンスや健康にとってマイナスです。
• 5-3. 鉄分・ビタミンC・アミノ酸・ミネラルも忘れずに
筋肉が合成されるためには、タンパク質だけでなく多くの栄養素が連携しています。
• アミノ酸:筋肉修復・エネルギー代謝・疲労回復を支える
•鉄分:酸素を筋肉細胞に運搬し、エネルギー代謝を支える
•ビタミンC:鉄分の吸収を高め、コラーゲン生成と筋肉修復を促す
•ミネラル(亜鉛・マグネシウムなど):筋肉の収縮やホルモン分泌をサポート。
普段の食事から摂取し続けるのは難しいため、私はこれらを一度に摂れる「サジー」が飲んでいます。 サプリに頼らず、朝の1杯で「使える栄養」を体にチャージできます。
• 5-4. 消化・吸収力の差にも注意
同じ量を摂っていても、「どれだけ効率よく消化・吸収できているか」は人によって差があります。
• 消化酵素の分泌量
• 食べるスピード
• 食物繊維や水分の不足
• ストレスによる胃腸機能の低下
こうした要因で、タンパク質が十分に使われないこともあります。
「食べた=使える」ではないことを理解し、自分の体の状態にも向き合うことが重要です。

筋トレは「筋肉だけ鍛えればいい」ではなく、「栄養・睡眠・思考」まで整えてこそ、結果が出る。
正しい知識があなたの身体を変える
一度に摂れるタンパク質は30gまで、そんな逸話を信じて、食事量を抑えていた頃の僕は、筋肉の成長も止まりがちでした。でも、科学的な情報と自分の体験から学び、必要なときに必要な量をきちんと摂ることの大切さを知ってからは、身体も気持ちも前向きに変わっていきました。
✅ 吸収量の上限を気にしすぎるより、トータルバランスと継続が大事
✅ タンパク質は「いつ・何と・どうやって」摂るかがポイント
✅ 一度に40gでも50gでも、必要なら堂々と摂っていい
大切なのは「これが正しい」と言われている情報を鵜呑みにせず、自分の身体で確かめながら、調整していくこと。これからもあなたの身体作りが、理論と実践の両輪で前に進むことを願っています。
【免責事項】
本記事の内容は、筆者が実際にサジー(豊潤サジー)を使用した体験に基づくものであり、特定の効果や結果を保証するものではありません。感じ方や体調の変化には個人差があります。
健康状態に不安がある方や持病のある方は、自己判断せず医師・専門家に相談した上でご利用ください。
【当サイトの運営について】
当サイトでは、商品紹介の際にアフィリエイトプログラムを利用しており、リンクを経由して購入された場合、運営者に報酬が発生することがあります。ただし、内容はステマではなく、実体験と正直な感想に基づいて作成しています。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4ddc6fed.e5f7cc15.4ddc6fee.62acc967/?me_id=1252285&item_id=10002388&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Frealstyle4u%2Fcabinet%2Fshouhin%2Fblp-s_line.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4dd60602.c5db1f78.4dd60603.8e763293/?me_id=1344477&item_id=10000008&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ffiness-saji%2Fcabinet%2F10750421%2Fsaji1000-mall_ver03.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメント